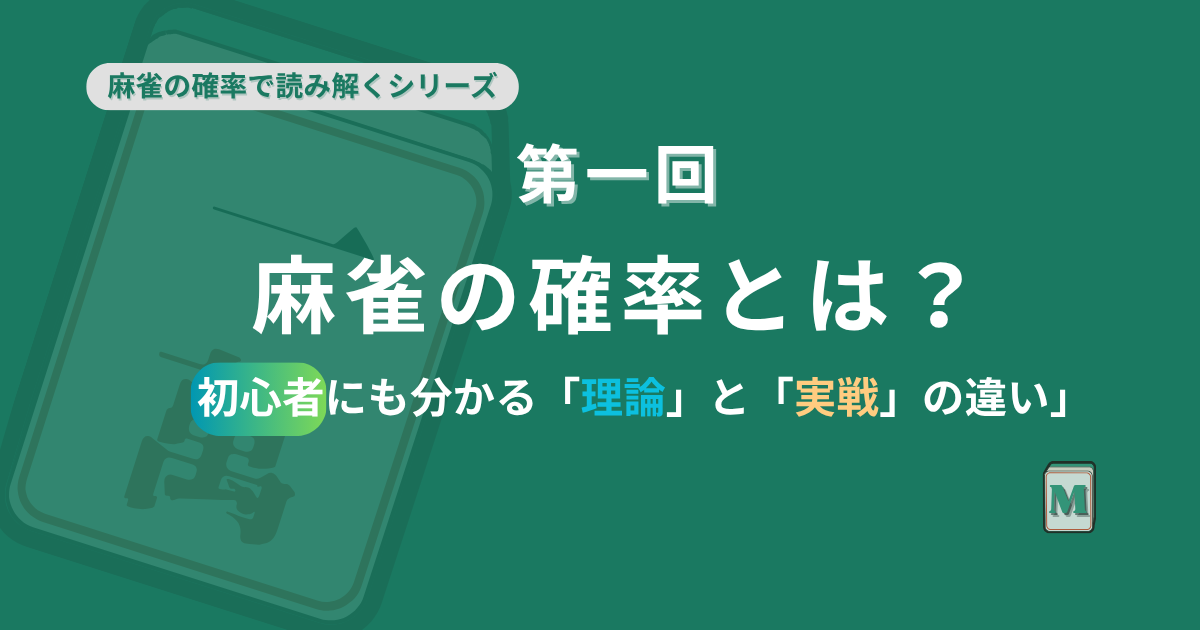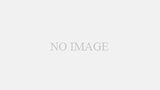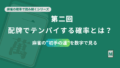はじめに:麻雀の確率って、意外と身近
麻雀を打っていると、自然と「確率」を考えています。
たとえば——
- 「この牌は通りそうだな」
- 「この待ちは山にまだありそう」
- 「そろそろ誰かテンパってる気がする」
実はこれ全部、確率を感覚で読んでいるんです。
この記事では、その“感覚”を「数字」で整理してみましょう。
1. 麻雀は確率のゲーム
麻雀の牌は全部で136枚。
配牌で52枚使うので、残りの山はおよそ80枚ほど。
この山から順にツモって、誰かがアガるまで進んでいきます。
つまり麻雀は、
「残りの山から、どの牌をいつ引けるか」
という確率のゲームなんです。
2. 理論の確率と実戦の確率
理論の確率(純粋な計算)
何も情報がない完全ランダムな状態での計算です。
たとえば、残り山が60枚で ![]() が3枚残っているなら、次のツモで引ける確率は 3 ÷ 60 = 約5%。
が3枚残っているなら、次のツモで引ける確率は 3 ÷ 60 = 約5%。
計算はシンプル。ちなみに「約5%」は“20回に1回”の当たり。
序盤の1ツモで引けなくても普通、という感覚に近いはずです。ツモを重ねるほど当たりやすくなります。
実戦の確率(状況を踏まえた確率)
実際の対局では、次のような情報が次々に増えていきます。
- 他家の捨牌
- フーロ(鳴き)の有無
- 局の進み具合
これらの情報をもとに、山にどの牌が残っていそうかを考え直していく。
これが「実戦の確率」、つまり条件付き確率です。
3. 「感覚」を確率で見てみると
麻雀を打ちながら自然にやっている“感覚的な判断”も、確率的に整理するとこう見えます。
| 感覚での判断 | 確率の見方 |
|---|---|
| 他家が2枚捨てているから、この牌はもう少ない | 残り山にその牌がある確率が下がる |
| 鳴きが多いから局が早く進みそう | ツモれる回数が減る |
| 終盤だから危険牌は切りづらい | 相手がテンパイしている確率が高い |
つまり、見えた情報をもとに確率を再計算しているということ。
みんなが自然にやっていることです。
4. 巡目で変わるツモ確率のイメージ
巡目が進むほど、1回ツモあたりの当たる確率は上がりますが、
残りツモ回数(チャンス)は減っていきます。
| フェーズ | 巡目 | 山に残る枚数 | 待ち3枚のツモ確率(1回) |
|---|---|---|---|
| 序盤 | 2巡目 | 約60枚 | 約5% |
| 中盤 | 8巡目 | 約40枚 | 約7.5% |
| 終盤 | 14巡目 | 約20枚 | 約15% |
終盤(14巡目)では、1ツモあたりの当たる確率が約15%まで上がります。
残りのツモは少ないものの、誰にでもツモるチャンスがある状況になり、場全体に緊張感が走ります。
確率が上がるほど局面も変わりやすくなる——体感してきた「終盤のアツさ」は、数字でもきちんと裏付けられているのです。
5. 確率が“感覚”を支えてくれる
麻雀は「運」に見えて、実は確率計算を都度し直した積み重ねです。
数字を通して見てみると、これまで感覚で捉えていた「流れ」や「読み」の中に、考え方の筋道があることに気づきます。
確率を知ることは、なんとなくの体感を、根拠のある体感へ変えていくこと。
数字を意識するだけで、打ち方や押し引きの選択に一貫性が生まれます。
- 根拠を持って押し引きできる
- 放銃を減らせる
- 役作りや手の進め方を冷静に選べる
確率を知ることで、考え方を広げるきっかけになるとうれしいです。
これまで“感覚”で打っていた部分に、少しだけ数字の視点が加わることで、
自分の選択に理由を持てるようになります。
それが、安定して強くなるための第一歩です。
次回予告
次回は「配牌で聴牌する確率」。
13枚の配牌の時点で、どれくらいの手がテンパイに近いのか?
数字で見ると、序盤の戦略がちょっと違って見えてきます。